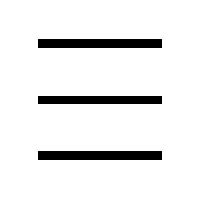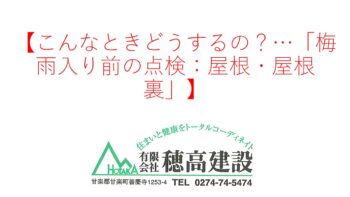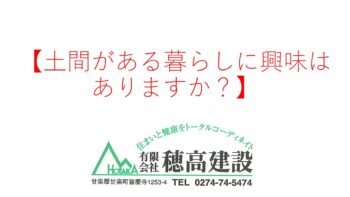【 その業者は『一貫体制』ですか? 】
こんにちは、皆さん。
業者選びについてお話しする時、私はよく『ハウスメーカー』と『工務店』に分類してお話しします。
今日は少し視点を変えて、『一貫体制』かどうかについて考えてみましょう。
ハウスメーカーといえば元請けが専門。
現場での施工は下請けに任せるのが一般的です。
下請け業者が複数いる場合、どの業者に任せるか皆さんが選ぶことはできません。
次に工務店です。
工務店といえば、契約前の打ち合わせから引き渡し後の定期点検まで全てを担うイメージがありませんか?
いわゆる『一貫体制』ですね。
しかし実際は、
・設計は社外の設計事務所に任せ、施工のみ行う
・ハウスメーカーの下請けのみ行う
・元請けとして機能し、現場は下請けの工務店に任せる
・建売住宅のみを手掛け、施主の意思を反映した住宅は扱わない
・フランチャイズとして制約の範囲内での施工を行う
など、さまざまなスタイルがあります。
業者のホームページを見ると、それぞれの家づくりについて記載されていますよね。
そこを読めば一貫体制かどうかがわかります。
もしわからない場合は、直接聞いてみましょう。
ところで皆さん、一貫体制にはどんなメリットがあると思いますか?
私が考えるメリットは、
・責任の所在がはっきりしている
・複数の業者の利益を負担しなくていいので、その分費用を節約できる
・社員間で情報の共有ができるので、万が一の際迅速に対応できる
・社員間で技術やアイデアの継承ができるので、それぞれの家づくりの経験を皆さんの家づくりに活かせる
などがあります。
こうして見ると、いいことだらけですね。
ただ、少しだけデメリットもあります。
それは、年間に施工できる棟数が限られることです。
複数の下請け業者と提携していれば、空いている業者に仕事を回せます。
しかし、自社の大工だけで施工する場合、大工のスケジュールが埋まっていれば、次の施主は待機するしかありません。
もし皆さんが家づくりを急いでいるのなら、これは大きなデメリットだと感じることでしょう。
今、あなたが気になっている業者の施工スタイルは一貫体制ですか?
一棟当たりの施工期間、一年間の施工棟数はどれくらいですか?
一度、調べてみましょう。
-

2025.07.03『夏の結露対策をしましょう』
-

2025.06.18『交通利便性だけでなく、生活利便性も確認しましょう』
-

2025.06.12『補助金や助成金を申請する際の注意点』
-

2025.06.03『住まいの暑さや寒さで苦労しているのなら』
-

2025.05.26『こんなときどうするの?…「梅雨入り前の点検:屋根・屋根裏」』
-

2025.05.23『土間がある暮らしに興味はありますか?』
-

2025.05.19『熟睡できる宿泊施設を試してみませんか?』
-

2025.05.02『こだわりが無いことに困っているなら』
-

2025.05.01『ごみ箱はどこに置く?』
-

2025.04.25『中古住宅を視野に入れるなら』
最新記事
- 07月03日 『夏の結露対策をしましょう』
- 06月18日 『交通利便性だけでなく、生活利便性も確認しましょう』
- 06月12日 『補助金や助成金を申請する際の注意点』
- 06月03日 『住まいの暑さや寒さで苦労しているのなら』
- 05月26日 『こんなときどうするの?…「梅雨入り前の点検:屋根・屋根裏」』